| 著書論文 | 通信制での実践 | 初任校での実践 |
|---|
紅水母熊虫
(べにくらげ くまむし)
(ベニクラゲ クマムシ)
( ペンネームの一つ )
[A高校定時制]
上位進学校へ異動の引き合いもあったのですが、家庭の事情により、初めて定時制高校に異動(異動要項では、全日制普通科へ必異動)しました。自分に勤まるだろうか、恐ろしいところではないだろうかと危惧していましたが、杞憂であることが分かり、不安は払拭できました(勤務しているうちに「定時制の学習院」と表現されるようになった時期もありました)。
今では当たり前ですが、最初から服務を厳正に守っていました。実際に仕事もたくさんありましたので、早い時間から出勤していました(別仕事で出勤中の朝10時頃、外部からの連絡により、生徒指導に対応したこともありました)。
予想はしていたことですが、板書の授業だけでは、生徒は授業にのってきませんでした。苦労して、試行錯誤を重ねた結果、前任校とは異なる新しい視聴覚教育方法をあみだしました。内容については、 「視聴覚教育実践」 に載っています。
また、 国際理解教育 の実践として、メキシコ人生徒や他教科教員とのTT(ティームティーチング)も行いました。この実践を含め、依頼により、 「米百俵とメキシコ」 (全国際研愛媛大会)というテーマなどで研究発表等も行いました。現代社会や政治経済の教育実践からは、依頼により、 「公民科に生かせる国際教育」 として公民科社会科教育全国協議会全国大会北海道大会でも研究発表するに至りました(実際の発表はB校異動後)。
長い教師生活中、担任を持たなかった年は1回だけでした。そうした中、たまたま4年(卒業学年)の副担任だった年の卒業式後、卒業生の保護者の皆様が感謝の意を込めて一席設けてくれていたことは感涙にむせびました。
在任中の後半は、管理職が入れ替わりました(研修研究と称する管外出張等に授業等をおいて特定の人達が出かけたり、生徒を置いて休暇手続き無しに特定の人達とノミュニケーションにでていく光景も見ました。そのようなことをする気にはなれませんでした。逆に休暇扱いで担任生徒保護者の告別式に出席、公費の香典や諸書類の持参と手続き等も行ったりしました。授業その他の校務には支障の無い日でした。また、当時は高体連選手登録は出張扱いという公的な基準になっていました。生徒達が不利益を受けないよう、登録は必ずしなければとの一心で、年休で登録参加しました。)。希望したわけではないのに、次第に「身代わり地蔵」のような存在に。すなわち、つるし上げ、スケープゴートの対象に転移。誰からも感謝されず、「労多くして功無し」。険悪歪構造の中、「癒着」という表現をしている人達もいました。使命感・責任感をもって心血を注ぐも、学校は荒れ、毎日対応に追われ、走り回る状態でした。最終電車も終わり、タクシーで帰らざるを得ない日々もありました。
・・・・・・ 五蘊盛苦。怨憎会苦。求不得苦。愛別離苦。
[B高校定時制]
青息吐息、満身創痍、傷心トラウマの中、家庭の事情により異動(異動希望は1年前にも出していたのですが、ようやく実現。なお、私がでた後の始業日?に突然亡くなったA校同僚がいました。 ・・・・ また、風の便りで小耳に挟んだところによると、A校トップは退職勧告を受け定年前に辞めたそうです)。
異動の校長面接前に、B校の職員組合校内委員から次のような指示がありました。
「1年の担任と生活指導部を希望すると校長面接で申し出るように」。
担任を連続してもっていたので、異動後もすぐに担任を引き受けるつもりでいました。1年の担任をするなら、生活指導部に属していた方がよいとも思っていました。
希望通り、異動元年に1年の担任かつ生活指導部員になりました。
なお、校長は面接前及び面接時に教務主任を考えていたということが後で分かりました。
異動してきた他の人達には担任があてがわれませんでした。
前からいる人は、担任にならないか又は1学年の修羅場を終えた学年の担任になりました。
1学年担任になった4月早々、空前絶後ともいうべき大事件が起きました。しかし、学年のチームワーク及び校長の毅然とした対応により、早期に無事解決しました。
担任パートナーにも恵まれていました。ベストパートナーでした。
しかし、パートナーは自宅から遙かに遠く通いきれないので、翌年異動してしまいました。
北海道から単身入学してきた担任クラスの生徒もいました。夏、北海道まで家庭訪問(自費ですので、正規のものではありません)に行き、ご両親と面談しました。成績や出席状況を北海道までこまめに郵送していましたが(近くに住んでいる人を含め、保護者全員に送っているものです)、卒業式でご両親にお会いした時、このことにも感謝の意を頂きました。
クラスの生徒達は、始業前・始業後とよく教室の掃除をしてくれました。
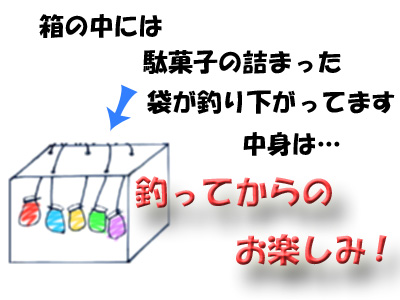 |
| 文化祭生徒作品 |
クラスの年配の生徒から、英語をどうしても身に付けたいという申し出がありました。他クラスや他学年の希望生徒達も集め、放課後その他通常の授業の無い時間に英語の学習指導を行いました(結果として年配の生徒比率が多かったです)。英語科教員ではないけれども、英語の教員免許状も持っていましたので、堂々と実行しました。
私の授業風景が突然(本人の承諾なく)、マスコミによって撮影されたこともありました。写真は 写真例 などで、 「マスコミ」 に載っています。
部活動としては、「国際交流部」を立ち上げ、ブラジルからの出稼ぎ者が多い群馬県の大泉町などへ生徒を休日に引率(交通費は自腹で、ブラジル料理レストランへ部員達を招待したりしました)もしました。また、外国籍生徒への日本語学習援助、地域のNPOとの連携事業なども行ったりしました。
授業持ち時数は一番多く、少ない授業時数専任教員の約2倍でしたが、苦にはなりませんでした。 学校の予算で研修研究の管外出張へ行っている人達もたくさんいましたが、 私は行きませんでした。多忙であり、授業を潰す気にもなれなかったことと、この種のものについては自費で行こうと考えていたためでした。
B校での実践例としては、 「校務実践」 や 「指定校実践」 があります。
私が異動することになった離任式後には、自分の学年の生徒のみならず、他の学年の生徒達も別れを惜しんでくれました。 そして、
「お金がないので、ほんの気持ちばかりだけど」
といいつつ、ちょっとしたものをプレゼントしてくれました。とてもうれしかったです。
先生方や事務の方々も私のためにお別れ会をしてくれました。世渡りがうまい人達はいましたが、「ノーメンクラツーラ」はいなかったと思います。
異動後1年目の卒業式は担任していた学年生徒が対象ではありませんでしたが出席しました。私が去ることに対して去年、別れを惜しんでくれた生徒達に会いたい一心でした。その次の年も連続して卒業式に出席しました。
異動後2年目も卒業式に出席しました。短い期間しか在任できませんでしたが、校長は良心に従い気を遣ったのでしょう、式辞の中で、2度も私に対する謝意を述べていました。 全く異例のことです(在任中、呼び出され大声で指導を受けていた教員が多い中、一度も怒鳴られたことがありませんでした。たぶん、怒鳴っても効果がないと思っていたのでしょう)。
司会による来賓紹介で、私が「卒業おめでとう!」と言うと卒業生達から歓声が沸き上がりました。 なお、私の次に紹介された人は、会場全体に向け、怒鳴り声をあげ何やらうったえていました。
式後、卒業生と語りあったことは勿論ですが、卒業生保護者の方々が私の顔と名前をよく覚えていてくれたことも嬉しいことでした。一度しか会ったことがない保護者の皆様でさえ、私の顔と名前をよく覚えていらっしゃいました。次々に「先生、お世話になりました」と声をかけてきてくれたことに感激しました。
本稿は日本国著作権法及び国際条約によって保護されています。再生・再発行(転送・プリントなどを含みます)等は著作権者の書面による許諾が必要です。
このページへのリンクは原則自由です。事前の連絡は必要ありませんが、リンクを行った場合は、こちらのページからリンク元のURLをご連絡ください。リンク元のホームページの内容が、法令や公序良俗に反する場合などにはリンクの削除をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。リンクを設定する際には、「定時制の思い出と実践」ホームページへのリンクである旨を明記してください。また、フレーム内に本サイトのページを表示させるリンク設定は行わないで下さい。
本サイト上の文書等の各ファイル、及びその内容は、予告なしに変更又は中止されることがありますので、あらかじめご了承ください。
| 著書論文 | 通信制での実践 | 初任校での実践 |
|---|