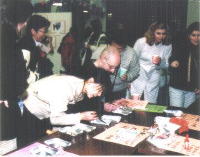
| お便りの角 | VISITOR'S BOOK | 校務実践 | 教育実践 |
|---|
1 研究指定校導入の経緯
4月からの着任のため、2月に新しい学校に面接に行った。この時印象に残っているのが、先生方の一部が人権教育をやらせてくれないかと管理職と話し合っていたことであった。
実際に4月に着任してみると、さまざまな国からの外国人生徒も在籍していた。私と同期着任者の中にも、中国語が得意で国際交流に関心を持っている先生がいた。この様な状況からすると、私が実践してきた「国際理解教育」ならば「人権教育」にも密接に関連している、管理職を含めた教職員全体の共通理解を得られると判断した。そして、「国際理解教育」のキャッチフレーズの下に教職員が一丸となって、教育への情熱・やる気を燃え上がらせることができるのではないだろうかと考えた。
ちょうど、新指導要領による新教育課程を決めなくてはならない時期に来ていた。着任2ヶ月の間に、国際理解教育を柱とした学校設定教科・科目12科目24単位を含む新教育課程を教職員の総意を得てまとめ、教育委員会における担当者の内諾も得た。翌年度の学校の教育目標に「国際社会に生きていくための資質と能力を育成する」という項目を加えるとともに、学校運営連絡協議会のメンバーに区役所の国際関係部門の管理職を迎えることができた。そして、国際理解教育推進の一環として、外国人とともに生きるNPO団体と連携し、文部科学省の「NPO等と学校教育との連携の在り方につ
いての実践研究」に関する研究指定校になることができた。申し込みは、推進スタッフ3名(校長の了解はとってあったが、校長も教頭もメンバーに入っていない)で申請した。それでも申請は通った。私が文部科学省関連のCD-ROM版著作などの実績があったので指定校として認められた部分もあったのではないだろうか。
2 研究内容
まず最初、教職員に対し、国際理解教育やNPO等に関する校内研修会を行った。「NPOとは何か」の説明に始まり、実際に携わった国際理解教育のビデオも見てもらうなど、視覚的な効果も考えた内容だった。また、教職員に対する校外研修会も2回実施した。
生徒達に浸透を図る第一段階として、生徒会生徒を数名の教員が引率する形で、校外見学会(NPO等の教育活動理解やNPO等外国人学習者との交歓)も行った。NPO等との交流活動を進めるため、NPO等の外国人学習者を学校に招き、生徒会及び部活動生徒等と合同でパソコン・インターネット学習や部活動合同練習を行い、交歓会も実施した。
学校主催のスポーツ大会や文化祭、NPO等主催の日本語教室「みんなの日」や「もちつき大会」でも交流・交歓を行った。
2月には 「国際理解ウィーク」 を設定し、NPO等と連携し、 「であう ふれあう かたりあう 地域からの国際理解」 というキャッチコピーのもと、世界の人々、文化、ことば等について知り、出会い、考え、体験する特別メニューの学校教育活動を行った。
なお、準備のため何度も校内打ち合わせやNPO等との会合を重ねた。
3 NPOとの連携
NPO等との連携の内容は、
①「総合的な学習の時間」において、生徒が学習を進める上で、NPO等から
必要な情報の入手方法、活用等についての研究。
②授業の改善に向け、NPO等と連携して、国際理解教
科・科目の教材の開発。
③NPO等との国際交流活動を通して、本指定校の教育活動を活性化するため
の方法・実践・教育効果・評価についての研究。
その他、NPO等の活動に生徒がどのように協力できるかなど、ボランティアの推進についての研究。
4 連携NPOについて
地域に暮らす外国籍の人々との共生を目指して、1992年10月に発足したNPOと連携した。
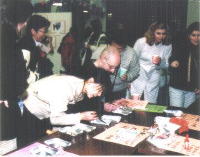 |